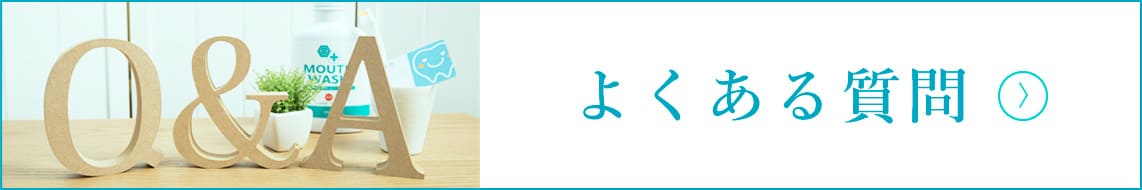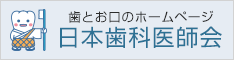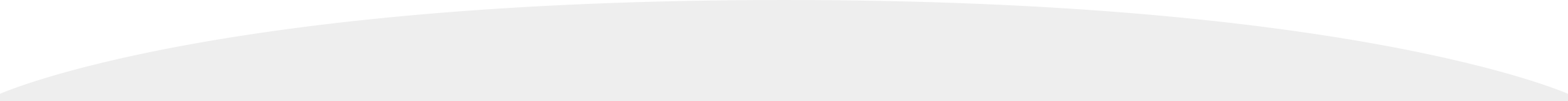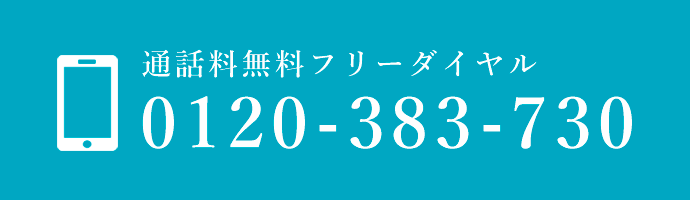Q. 子どもの「お口ぽかん」、そのままでも大丈夫?
A. 放っておくと歯並び・姿勢・集中力にも影響します。早めのチェックが大切です。

最近、「テレビを見ているとき」「スマホやタブレットを使っているとき」に、気づくとお口がぽかーんと開いている――そんな“お口ぽかん”のお子さんが増えているのをご存じですか?
マスク生活や柔らかい食べ物、長時間のスマホ姿勢など、現代の生活習慣がその背景にあると言われています。
こうした“お口の育ち”に関する問題は全国的にも注目されており、2024年度から「小児口腔機能発達不全症」として治療の対象になりました。
つまり、「うちの子、気になるけど相談していいのかな?」と思っていた保護者の方も、
安心して歯科でチェックやトレーニングを受けられる時代になったということです。
「気づくといつも口が開いている」「寝ているときも口呼吸やいびきをしている」
そんな“お口ぽかん”は、見た目の問題だけでなく、歯並び・姿勢・集中力など
お子さんの発達全体に関係していることがあります。
この記事では、山形市のごとう歯科・矯正歯科クリニックが、お口ぽかんの原因・影響・家庭でできるケア・歯科でのサポート方法を、やさしく丁寧にご紹介します。
目次
お口ぽかんってなに?
「お口ぽかん」は、「口唇閉鎖不全」と言い、本来口を閉じているべきときにも無意識に唇が開いたままになっている状態のことを指します。
実は、年齢を問わず多くの子どもたちに見られ、最近では3人に1人が当てはまるとも言われています。
「癖みたいなもの」と思われがちですが、実際にはお口の筋肉や呼吸の使い方に原因があります。
つまり、自然に治るものではなく、正しい使い方を“育てていく”必要があるサインなのです。
お口ぽかんの主な原因

1. 鼻呼吸がしにくい
鼻づまりやアレルギー、扁桃肥大などで鼻呼吸が難しくなると、口で息をする“口呼吸”が習慣になります。鼻呼吸ができない状態が続くと、口呼吸によりお口まわりの筋肉が弱くなってしまいます。
2. 舌や唇の筋肉の発達が未熟
舌が下に落ちたままだと、上あごを押さえる力が弱くなり、口が自然と開いてしまいます。柔らかい食事が多い現代では、噛む回数が減って筋肉が育ちにくい傾向があります。
3. 姿勢や生活習慣の影響
前かがみの姿勢や長時間のスマホ・タブレット操作も要注意。頭が前に出ると気道が狭くなり、無意識に口を開けて呼吸しやすくなります。
4. 唇を閉じる習慣が育っていない
「閉じなきゃ」と意識することがないと、唇を閉じる筋肉が鍛えられません。家でもテレビを見たり、口を開けたままぼーっとする時間が増えると、次第に“お口ぽかん”が定着していきます。
放っておくとどうなるの?

1. 虫歯・歯肉炎が起こりやすい
口が開いていると乾燥しやすく、唾液の力が働きにくくなります。
唾液は本来、口の中を洗い流して細菌を抑える“天然のうがい薬”。
これが少なくなると、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。
2. 歯並び・噛み合わせへの影響
舌が低い位置にあると、前歯を押し出す力が働きやすく、出っ歯や開咬の原因に。
また、上あごの発達が十分でないと、歯が並ぶスペースが狭くなってしまいます。
3. 顔立ちや姿勢への影響
口を閉じる筋肉(口輪筋)が育たないと、あごが下がり、「ぽかんとした表情」「面長傾向」になることがあります。
また、頭が前に出た姿勢が定着すると、猫背や肩こりの原因にもなります。
4. 集中力・睡眠の質の低下
口呼吸が続くと、脳への酸素供給が減り、集中力が落ちやすくなると言われています。
睡眠中も口が開いていると、いびきや眠りの浅さにもつながります。
歯科でできるサポート
「お口ぽかん」と聞くと矯正治療を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、多くの場合、まずは**“お口の機能を育てる”トレーニングや生活習慣の見直し**から始めます。
1. お口の機能チェック
舌や唇、頬の動き、呼吸の様子、姿勢などを一つひとつ丁寧に確認。
どの部分の発達が追いついていないかを一緒に見ていきます。
2. 口腔筋機能トレーニング(MFT)

専用の装置や木のスティックやストローを使った練習、「あ・い・う・べ体操」など、遊びの延長でできる練習を取り入れます。
これらのトレーニングは「筋肉を強くする」だけでなく、
“正しい舌の位置”や“鼻呼吸の習慣”を身につけることが目的です。
3. 生活習慣のアドバイス
食事中の姿勢、噛む回数、寝るときの姿勢など、家庭でできることを保護者と一緒に確認し、サポートします。
2024年度から「小児口腔機能発達不全症」が保険適応に!

この制度により、歯科での評価・トレーニング・経過観察が正式に保険で行えるようになりました。
つまり、気になる段階からでも気軽に相談が可能になったということです。
山形市のごとう歯科・矯正歯科クリニックでは、小児歯科と矯正歯科が連携し、成長段階に合わせたお口の機能サポートを行っています。
「治す」よりも「育てる」を大切に、やさしく寄り添うケアを心がけています。
ここで登場!「りっぷるくん」

当院では、お口を閉じる力を育てるサポートとして「りっぷるくん」というトレーニング機器を使っています。
りっぷるくんでは、トレーニングの前と後でお口の力を数値で確認できるので、「がんばった分の変化」が目に見えてわかります。お子さん自身も「強くなった!」と実感でき、やる気につながります。
トレーニングはゲームのように楽しく取り組める内容で、小さなお子さんでも無理なく続けられるのが特徴です。楽しみながらお口のまわりの筋肉をきたえることで、自然に口を閉じる力や鼻呼吸の習慣が身についていきます。
“お口を育てる”ためにお家できることはある?
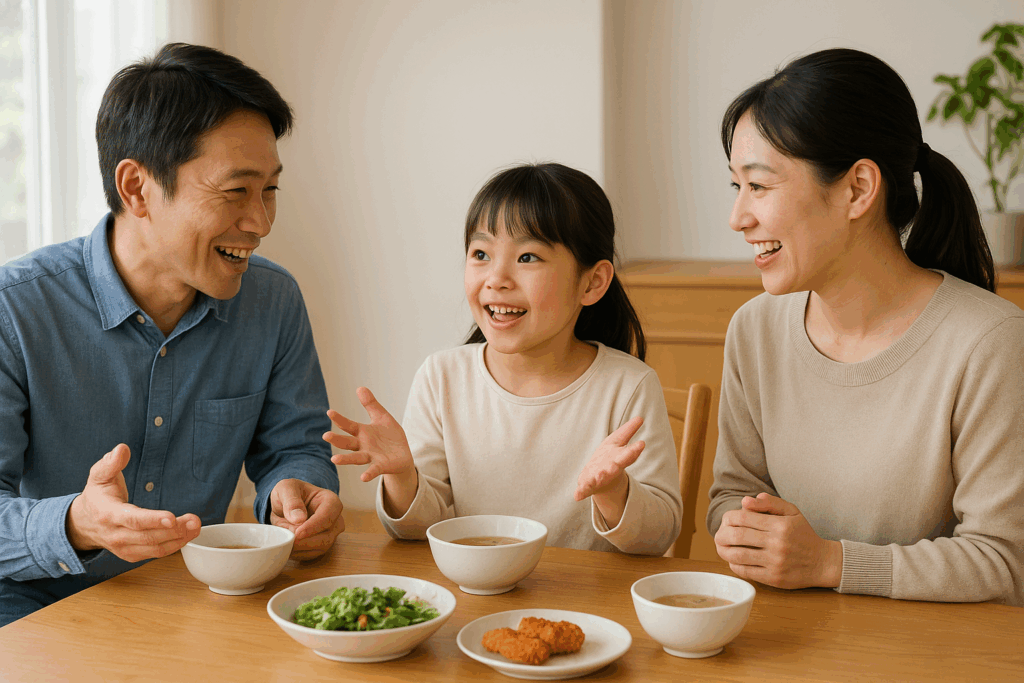
お口ぽかんは、家庭でも少しずつ改善していけます。
大切なのは、“無理なく続けられること”を毎日の中に取り入れることです。
まず、姿勢を整えること。
食事のときは、足が床につく高さの椅子に座り、背中をまっすぐに。
姿勢が安定すると、あごの動きや呼吸が整いやすくなります。
次に、鼻呼吸の練習をしてみましょう。
口を閉じて「スーッ」と鼻で吸い、ゆっくり鼻から吐く。
1日数回でも意識するだけで、鼻で呼吸する感覚が育ちます。
ハミングをしたり、風船をふくらませる遊びもおすすめです。
食事では、よく噛む食材を選びましょう。
にんじん・ごぼう・りんご・おにぎりなど、
噛み応えのあるメニューを取り入れると、舌や頬の筋肉が自然に鍛えられます。
また、寝るときの姿勢も大切です。
枕を高くしすぎず、仰向けで寝ることで舌が上あごにおさまり、鼻呼吸しやすくなります。
そして何より、家族での会話を増やしましょう。
おしゃべりは「楽しい口の運動」です。
テレビやスマホを見ながらの食事を減らし、顔を見て話す時間が増えるだけでも、お口の筋肉や発音、息の使い方が自然と育ちます。
FAQ(よくある質問)
Q1. トレーニングは難しいですか?
A. いいえ、お口のトレーニング(MFT)は難しい動きではなく、楽しみながら少しずつ筋肉を鍛えていくので、小さなお子さんでも無理なく続けられます。当院では、年齢や性格に合わせて「できた!」という成功体験を積み重ねられるよう工夫しています。親御さんも一緒に取り組むことで、家庭でも楽しく続けやすくなります。
Q2. 家でもできることはありますか?
A.はい、 ご家庭でできることもたくさんあります。まず大切なのは、姿勢を正しく保つこと。猫背や頬づえはお口の筋肉を弱くし、口呼吸の原因になります。また、「よく噛む」「鼻で呼吸する」「話すときはしっかり口を動かす」といった日常の積み重ねが、自然なトレーニングになります。テレビやスマホを見ながら食べるより、家族で会話しながら食事を楽しむことも、お口の筋肉や発音の発達に効果的です。小さな習慣の積み重ねが、お口の成長を大きく変えます。
Q3. 保険で受けられますか?
A. はい、「小児口腔機能発達不全症」と診断された場合は、保険適用で治療や指導を受けることができます。この診断は、噛む・飲み込む・発音する・呼吸するといったお口の機能に問題が見られた場合に下されます。診断基準に沿って歯科医師が総合的に判断します。保険の範囲内で、トレーニング指導や生活習慣のアドバイスを受けられるため、気になる症状がある場合は早めに相談するのがおすすめです。自費治療に比べて費用負担も少なく、安心して継続できます。
Q4. 大人になってもお口ポカンは治せますか?
A. はい、大人でも改善は可能です。ただし、骨格や筋肉の発達が落ち着いているため、子どもの頃よりも時間がかかることがあります。お口ポカンの原因は、舌の位置・唇の力・鼻呼吸のしづらさなどさまざまです。原因を見極めたうえで、MFT(筋機能療法)や呼吸トレーニングを行うことで、姿勢や口元のバランスが整い、自然と口が閉じやすくなります。成長期に始める方が改善しやすいですが、大人でも継続すればしっかり効果が出ます。
まとめ
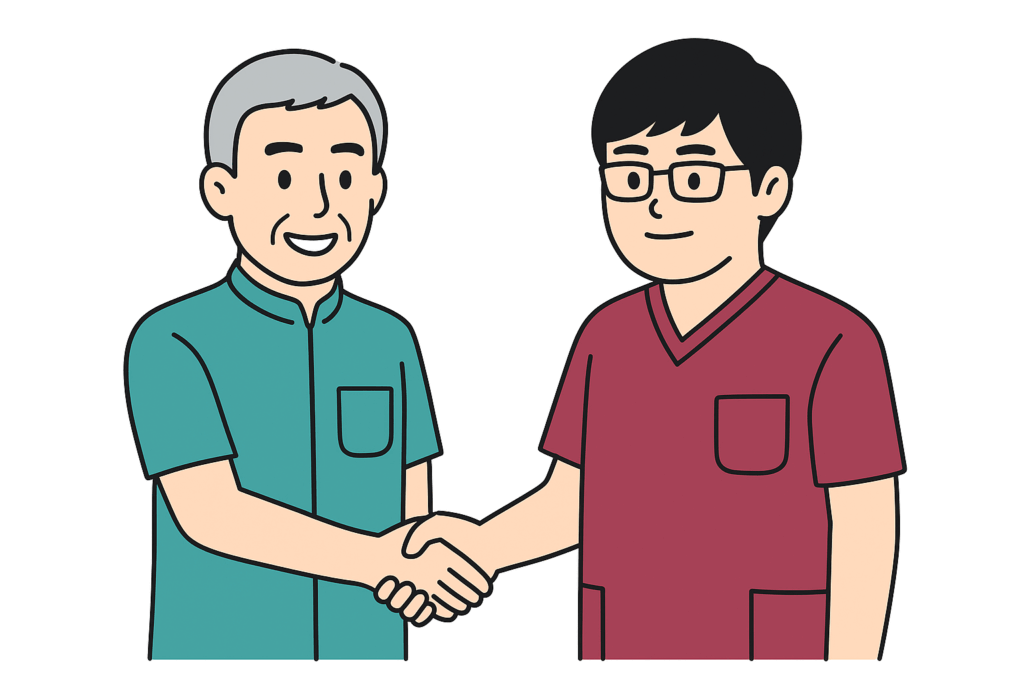
お口ぽかんは、「かわいい癖」ではなく「成長のサイン」。
気づいたときにサポートを始めれば、歯並び・呼吸・姿勢などお子さんの発達すべてを良い方向に導くことができます。
山形市のごとう歯科・矯正歯科クリニックでは、小児と矯正の両分野が連携し、成長に合わせたやさしいサポートを行っています。
「うちの子ももしかして?」と思ったら、どうぞお気軽にご相談ください。
こちらのブログではこれからも、矯正治療や歯科治療に関する情報を発信していきますので、皆様のお口の健康に少しでも役立てていただけますと幸いです。
山形市での矯正はごとう歯科・矯正歯科クリニック✨🍀
👉ごとう歯科・矯正歯科クリニック公式LINEアカウント:https://lin.ee/UAGDkMQ
小児歯科についてもっと知りたい方はこちら:小児歯科 | ごとう歯科・矯正歯科クリニック
過去のおすすめ記事:矯正後に歯は戻るの?後戻りを防ぐリテーナーの役割とは | ごとう歯科・矯正歯科クリニック