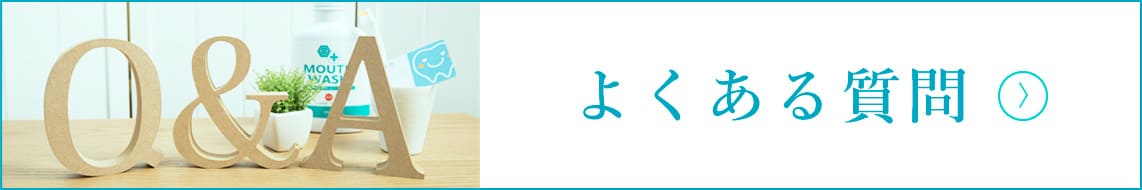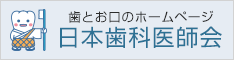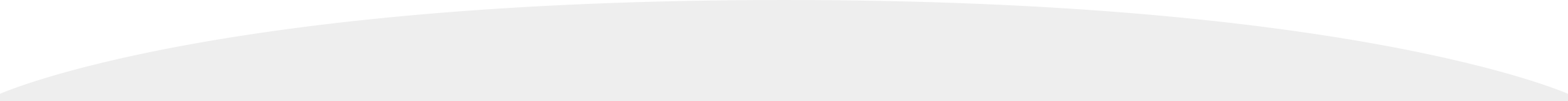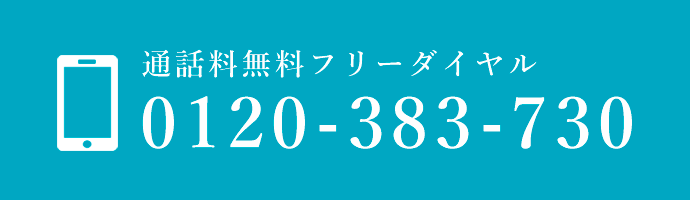皆様こんにちは!山形市の矯正歯科「ごとう歯科・矯正歯科クリニック」です🦷🪥
近年、街中や学校、公共施設などでよく見かけるようになった「AED(自動体外式除細動器)」。
病院や歯科医院ではほぼ必ず設置されており、いざという時に患者さんや来院者の命を救う大切な医療機器です。
しかし、実際に使ったことがある人は少なく、「どんな機械なのか」「自分でも本当に操作できるのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、AEDの役割や必要性、設置場所、実際の使い方、注意点、心肺蘇生(CPR)との関係、そして今後の普及に向けた課題について詳しく解説します。
医療機関を訪れる患者さんにとっても、日常生活を送る上での安心材料になるはずです。
目次
AEDはどんな機械?

AEDとは「Automated External Defibrillator(自動体外式除細動器)」の略称で、心臓がけいれんするように小刻みに動き、血液を全身に送り出せなくなる「心室細動」という状態に対して電気ショックを与え、正常なリズムを取り戻すための医療機器です。
特徴的なのは、専門知識のない一般市民でも使えるように設計されている点です。
電源を入れると音声ガイドが流れ、電極パッドを胸に貼る場所や、ショックが必要かどうかを自動で判断してくれます。
そのため、医療従事者でなくても、手順に沿って操作すれば適切に使用できるのです。
AEDが必要とされる理由

心停止は突然起こります。
日本では毎年数万人が心原性の突然死で命を落としているといわれており、その多くは病院外で発生しています。
救急車が到着するまでには平均で8〜9分かかるとされますが、その間に何もしなければ生存率は急激に下がってしまいます。
特に心室細動を起こしている場合、1分ごとに生存率が大きく下がることが知られています。
逆に、心停止直後にAEDで除細動を行えば、救命率は飛躍的に高まります。
つまり、救急車を待つだけではなく、その場に居合わせた人がAEDを使えるかどうかが生死を分けることになるのです。
歯科医院とAEDの関係

「心臓に関係する病気は内科や循環器科では?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、歯科医院でも体調不良は起こりえます。
・診療に対する不安や緊張による発作
・治療中の急な血圧変動
・高齢の方や持病をお持ちの方の体調急変
・麻酔薬に対する反応
こうした場合、まれに心停止に至ることも考えられます。
そのため、歯科医院でもAEDを備えておくことが、患者様の安全を守るうえで欠かせないのです。
AEDはどこに設置されている?

👆当院では受付に設置されています。
AEDは病院や歯科医院をはじめ、駅や空港、学校、ショッピングモール、スポーツ施設など、多くの人が集まる場所に設置されています。
最近ではコンビニやオフィスビルにも導入が進み、日常生活のさまざまな場面で目にする機会が増えました。
設置場所には赤いハートマークに稲妻が描かれた国際的なシンボルマークが使われており、一目でわかるようになっています。
災害時やイベント会場など、臨時で設置されるケースもあり、緊急時に誰でも手に取れる位置に置かれているのが基本です。
AEDの使い方

実際にAEDを使う場面を想像すると難しく感じるかもしれませんが、手順はとてもシンプルです。
- 周囲の安全確認と意識の確認
倒れている人がいれば、まず周囲が安全かを確認し、声をかけて意識があるかどうかを確かめます。 - 応援と119番通報
周囲に人がいれば協力を求め、119番通報とAEDの手配をお願いしましょう。 - 呼吸の確認
正常な呼吸がなければ心停止と判断します。 - AEDの到着と電源オン
電源を入れると音声ガイドが流れます。 - パッドの装着
ガイドに従って、胸部に電極パッドを貼ります。 - 心電図解析とショック
AEDが自動で心電図を解析し、必要な場合は「ショックを行ってください」と指示します。その際は周囲の人が患者に触れていないことを確認してボタンを押します。 - 心肺蘇生の再開
ショック後も心拍が戻らない場合は、胸骨圧迫と人工呼吸を続けます。
このように、AEDは使用者が迷わないよう丁寧に音声で案内してくれるので、落ち着いて行動することが大切です。
AEDを使うときの注意点
AEDは安全に設計されていますが、いくつか注意すべきポイントがあります。
- 水濡れしている場合は拭き取る:胸部が濡れていると電気が拡散するため、タオルで軽く拭いてからパッドを貼ります。
- 子どもへの使用:小児用パッドが用意されている場合はそれを使用します。なければ成人用でも構いません。
- 体毛が濃い場合:電極が密着しない場合はシェーバーで処理してから貼ることがあります(多くのAEDに同梱)。
- ペースメーカーや金属製品:体内にペースメーカーがあっても使用可能ですが、パッドは少し離して貼ります。ネックレスなどは外すのが望ましいです。
AEDと心肺蘇生の関係

AEDだけでは十分ではなく、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を組み合わせることが重要です。
AEDが到着するまで、またショックを行った後も、心臓が再び動き出すまで胸骨圧迫を続ける必要があります。
胸骨圧迫は1分間に100〜120回のテンポで、胸が約5センチ沈む程度の強さで行います。
人工呼吸ができればより効果的ですが、感染症への不安がある場合は胸骨圧迫だけでも構いません。
AEDと心肺蘇生を組み合わせることが、救命率を最大限に高めるポイントです。
講習はどこで受けられる?

AEDの講習は、消防署や日本赤十字社が主催する一般向けの救命講習で受けられるほか、自動車教習所でも受講する機会があります。
最近では普通自動車運転免許の取得課程に「応急救護処置」の講習が含まれており、心肺蘇生法とあわせてAEDの使い方を学ぶことができます。
地域の自治体や消防本部のホームページなどで日程を確認し、申し込みをするのが一般的です。
こうした機会を利用して、突然の緊急事態にも落ちついて対処できるように体験してみてはいかがでしょうか。
AEDの普及状況と今後の課題

日本では2004年から一般市民によるAED使用が認められ、全国で急速に普及しました。
駅や商業施設での設置率は高まり、学校教育でもAEDの使用方法が取り上げられるようになっています。
しかし、実際に現場でAEDが使用される割合はまだ十分とはいえません。
「自分にはできない」と感じて使われないケースや、設置場所がわかりにくいという課題もあります。
また、機器の定期点検やバッテリー交換など維持管理の重要性も指摘されています。
今後はさらに設置場所を増やすだけでなく、地域住民や医療機関、学校での講習を通じて「誰でも使える」という意識を広めることが求められます。
まとめ
AEDは、突然の心停止から命を救うために欠かせない医療機器です。
専門的な知識がなくても音声ガイドに従って操作でき、心肺蘇生と組み合わせることで救命率は大幅に向上します。
病院や歯科医院を訪れる患者さんにとっても、「ここにはAEDがある」という事実は安心につながります。
万が一の事態に備えて、AEDの存在を知り、基本的な使い方を理解しておくことが大切です。
私たち一人ひとりが知識を持ち、勇気を持って行動できる社会を目指していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
こちらのブログではこれからも、矯正治療や歯科治療に関する情報を発信していきますので、皆様のお口の健康に少しでも役立てていただけますと幸いです。
山形市での矯正はごとう歯科・矯正歯科クリニック✨🍀
👉ごとう歯科・矯正歯科クリニック公式LINEアカウント:https://lin.ee/UAGDkMQ
当院についてもっと知りたい方はこちら:山形市の歯科・歯医者・矯正歯科・咬合治療なら「ごとう歯科・矯正歯科クリニック」
過去のおすすめ記事:医療費控除ってどんな制度? | ごとう歯科・矯正歯科クリニック